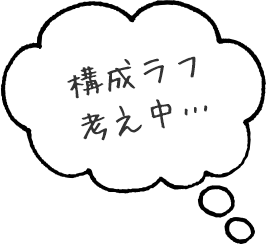クライアントにヒアリングし、制作するWebサイトのゴールを決め、その目標を達成するための戦略設計やサイトマップもクライアントから承認をもらえたら、いよいよWebサイトの実制作が始まります。
制作の最初に行うことが、スタッフとのキックオフ。その際に用意したいものが要件定義書です。この記事では要件定義書に何を書けばよいのか、必要な項目について紹介します。
目次
「要件定義」とは、主にWeb制作やシステム開発などのプロジェクトがスタートする際、開発担当者や関係スタッフが知っておくべき情報をわかりやすくまとめる作業のことを言います。
例えば、「なぜこのサイトを制作することになったのか」の制作背景や、最終的な数値目標とその期限、サイト全体のコンセプト、イメージしているデザイン(世界観)、実装したい機能、サーバー要件、公開後の運用方針など……。
サイト構築の中で共有しなくてはいけない情報や制作・開発要望をまとめていきます。
要件定義を制作するタイミングとしては、クライアントに提案した戦略設計・サイトマップが無事承認をいただいた後、実制作がスタートする前のタイミングです。
Webサイトの場合の要件定義は、主に下記のような項目について、制作スタッフにきちんと伝わるようわかりやすく記載します。
クライアントにヒアリングした内容から、このWebサイトを作る目的、現状の課題や要望、商材やサービスの強みや独自性、クライアントを取り巻く市場状況や業界の慣習、競合についてなどをなるべく書くようにしましょう。
製作スタッフにもクライアントのことや、サイトの中で訴求する商品やサービス、その業界について深く理解しておいてもらうことは、デザイン制作やプログラミングなどの際の判断の参考になるはずだからです。
KGI(Key Goal Indicator)は「重要目標達成指標」、KPI(Key Performance Indicator)は「重要業績評価指標」を指します。要は、Webサイトを制作することで最終的に達成したい目標数値がKGI、その目標を達成するのに欠かせないプロセスの達成度合いを計測するための数値指標がKPIです。
期日内で納品をすることはもちろん、サイトクオリティを高めること、コンセプトのぶれないサイト制作を進めていくためにも、KGI・KPIは関わる制作スタッフ全員が認識していなくてはなりません。
基本情報として、Webサイトの納品日、テストアップ予定日、制作予算を記載します。
制作日程については、全体の詳細がわかるスケジュールが用意できればベストですが、仕様が決定していないなどで詳細未定の場合は、ざっくりでも、デザインはいつ頃から、コーディングはいつ頃から開始する、など、担当ごとの作業開始日想定がわかると良いでしょう。
Webサイトには様々なユーザーが訪れますが、その中でもクライアントがとくに出会いたいと思っているユーザーや、これから獲得していきたいと思っているユーザーなど、訴求商材とマッチする見込み客・ターゲット層は誰なのかの設定を詳しく記述します。
サイト全体の主題・テーマが何かを明示します。どんなユーザーに対しどんな価値を届けるサイトなのかをわかりやすく記したものです。
例えば「ライザップ」のコンセプトは「これまで痩せられなかった人が、確実になりたい身体に変われるジム」であり、そのコンセプトを表現したキャッチコピーが「結果にコミットする」なのですね。
同じように、誰に対して何(どんな価値や満足)を提供するWebサイトなのかを記載してください。
ターゲットユーザーやサイトのテーマ(コンセプト)、商材の特徴、クライアントの要望やブランドイメージなどを鑑み、希望するデザインの方向性を記載します。
参考となる具体的なWebサイトやデザインの本などの資料を用意すると、よりイメージを共有しやすいでしょう。
画像やテキストはクライアント側からいただけるのか、制作側で取材や撮影を行うのか、原稿執筆またはライターへの発注が必要なのかを記載します。
制作側で写真を撮影する場合、カメラマンは誰に依頼する予定か(未定ならどのように選定するのか)、レタッチ(画像の色の補正や汚れの除去)作業はカメラマン側で行うのか、デザイン側で作業するのかなど、細かい点まで想定を記載します。
ライティングも同様で、執筆をはじめ、編集やテキストの流し込みは誰が行う予定かなど、最初に担当者が決められていれば、制作スタッフも予定が分かり安心できます。
動画やアニメーションなど、なんらかの別途制作が必要な場合は、要件定義に書きましょう。動画制作スタッフやアニメーション制作スタッフはどうするのか、制作期間、どのような内容か(ざっくりでよいので)、想定している長さ、公開先(youtubeか、サイトへの埋め込みか)など、わかることはすべて書きましょう。
日本語だけでなく、英語などの外国語切り替えをしたい場合はその旨を記載します。
この場合、外国語への翻訳原稿は誰が用意し、いつどのように納品されるかまで検討したほうが良いでしょう。
サイトの中に実装したい機能を記述します。
例えば、アコーディオンメニュー(クリックするとコンテンツが表示されたり隠れたりする)、モーダルウィンドウ(元の画面の上に別ウィンドウで画面を表示させる)や、ページネーション(1ページを分割し、分割した各ページへの送りリンクをつける)、複数の画像をスライドして表示させるスライドショーなどなど。
ページの画面設計を描く構成案と一緒に合わせて機能の詳細も書き込むケースもあります。
ブラウザとは、Webサイトを閲覧するために利用するソフトのことです。
例えば「Internet Explorer(IE)」「Google Chrome」「Safari」「Firefox」「Microsoft Edge」「Opera」などがよく利用されています。スマートフォンなら、iPhoneであれば「Safari」、Androidなら「Google Chrome」が標準搭載されているので、それぞれ使用している人が多いと思います。
それぞれのブラウザソフトはアップデートでバージョンが上がっていきますが、そこで必要になってくるのが「どのバージョンまでを想定してWebサイトを制作するか」の決定です。
基本的には各デバイスが定めているサポート期間内のバージョンは対象内とすべきですが、状況によっては対応範囲をある程度狭めることもディレクション側が判断しなくてはいけません。
自社サーバーを使用するのか、業者に申し込んで借りるレンタルサーバーを利用するのか、共用サーバー・VPS・専用サーバー・クラウドサーバー……どれを使用するのかなどなど、サイト規模や実装したい機能(個人情報を取得したい、など)によって、エンジニアと良く相談する必要があります。
公開した後にサイトをどのように運用する予定か、制作前の段階から想定・準備ができていると、納品後の運用フェーズにスムーズに入ることができます。

要件定義書は誰が見ても分かりやすく、イメージしやすく工夫して作成したいところですが、これらを制作スタッフに説明する際には、ぜひ熱意をもって話をしましょう!
クライアントと直接お会いし、経営者や担当者からWebサイト発注の背景や大きな期待、深刻な悩みなどをお聞きしているWebディレクターは「何としてもこのプロジェクトを成功させたい!」と強く思うものですが、ほとんどの場合、その場に制作スタッフは同席していません。
ただし、制作スタッフたちが当事者意識に燃え、「成果の出るサイトを作るぞ!」と奮起してベストパフォーマンスを出してくれなくては、クライアントの期待を超える成果を出すことは難しいもの。このため、間に立つWebディレクターが、制作スタッフたちへサイト要件を共有するミーティングで、制作スタッフたちの熱量を思いきり高める時間づくりを心がけましょう!


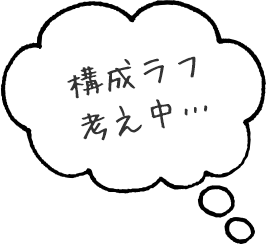

「Webサイト制作ってどう進めているの?」
「Webディレクターはどんな仕事をするの?」
これを読めばイメージが掴めます!
クライアントの課題解決のために、市場を分析、ターゲットを設定して企画を練り、コンテンツを創るWebディレクター。…と言われても、「Web制作がよくわからないから、いまいちイメージが湧かない!」という皆さんに、新人Webディレクターの一日を追いかけながら、Web制作の現場やWebディレクターの仕事の一部をご紹介します♪

さとゆり
前職はラジオディレクター兼ライター。Web業界未経験でWebディレクターになり丸1年♪ガッツと取材力が武器!